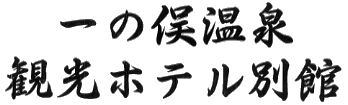
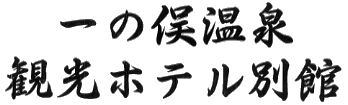
 |
平成の大合併で下関市になった豊田町の一の俣温泉。市とは名ばかりの山間地にある温泉地。比較的規模の大きいホテルが2軒。それ以外にも小規模の温泉宿が点在。先達の推薦はないものの、玉石混交の『山口の温泉』(ザメディアジョン、2005年)から自分自身で本物を見極めようと初挑戦。「浴室いっぱいに硫黄の香り」という紹介文を手がかりに観光ホテル別館へ。
一の俣温泉に近づくと、最も手前に観光ホテル別館への入口があります。右手にグランドホテルが見えたら赤い欄干の橋に着く前に左手の坂道へ。入口に色あせた大きな看板がありますが、建物は確認できません。坂道の途中まで進んで左手を見上げると、やっと観光ホテル別館が見えてきます。【上掲画像】宿泊棟の左手、スレートの建物が浴室。坂道を登りきってUターンしたところが玄関。
玄関を入るとフロントは無人。声を掛けても反応はなし。カウンターの呼び鈴を鳴らすと、しばらくして白衣の板前さんらしき方。入浴のお願いをすると、「おふろー、おふろー」と奥に向かって声を張り上げていらっしゃる。やっと登場されたフロント担当の年配のご婦人。ま、こんな感じです。いいんですよ、お目当ては浴室のお湯なんですから。
廊下の突き当たりが浴室の入口。訪問した日は、右の山側が男湯、左の谷側が女湯。脱衣場は窮屈で、透明ガラス戸のすぐ先が浴室。浴室に入って印象的なのが鉄骨とスレートの構造。鉄工所か何かと間違いそう。男湯と女湯の仕切りも大雑把。どういうわけか、浴室内の窓際にソテツが数本。昔懐かしいジャングル風呂のイメージでしょうか。

浴室の広さにもかかわらず、浴槽はアンバランスに小さい。【画像上左】縁の一部に切り欠きがあり、お湯が流れ出ています。滔々という感じではありませんが、確かにかけ流しです。湯口は直接浴槽に流入するタイプ。【画像上右】手をかざすと熱いお湯が流れ込んでいます。
「浴室いっぱいに硫黄の香り」という『山口の温泉』の記述はやや大袈裟。それでも浴槽のお湯からはっきりと硫黄臭を確認することができます。そして何よりこのヌルヌル感。これがすばらしい。思わず、ニンマリ。アルカリ度ph9.93の湧出地のデータは、浴槽でもその効果が十分確認できます。素人にも分かりやすい温泉ですね。

浴室の隅にさらに小さな浴槽。【画像上左】冷水ですが、これが加温前の源泉なのでしょうか。一応入ってみましたが、香り、味、アルカリ度など、確信が持てません。ひょっとするとただの井戸水かも。それにしては透明感がありますね。浴室の窓を開けて見上げると、貯水タンク、煙突、可燃物貯蔵所の看板。加温施設なのでしょうかね。【画像上右】
お風呂上がりに冷水風呂についてフロントで確認しようとしましたが、どうも要領を得ません。例の板前さんにも尋ねてみましたが、「知らない」とのこと。フロントのご婦人同様ほとんど関心がなさそうです。はて。フロント周辺の掲示物に目を凝らすと何となく事情が見えました。旅館業の認可は別名称。ははあ〜ん。事情があって、隣接の観光ホテルに吸収されたのでしょうか。それで「別館」。
ま、詮索はやめましょう。分析表の追加事項には「加温」「塩素」。かけ流しで塩素消毒のこともあるのでしょうか。ある情報によれば、現在一の俣温泉のすべての施設は同一源泉からの集中給湯になっているとか。残念ながら、源泉地の確認もできず、もろもろ課題が残りました。
同行した奥さまによると、女湯の浴槽は熱すぎて入るのに苦労したとか。目一杯蛇口をあけて水を入れたそうです。これって「加水」ですよね。温度管理が十分でないのかもしれません。確かに見晴らしはよかったそうですが、外からも丸見え。あちゃっ。ソテツも数本あったそうです。
湯上り後、山道を散策しているとこんな石碑に遭遇。「いのしし塚」。そうです、一の俣温泉はイノシシが名物。シシなべですね。というか、イノシシが出るようなところというのが真相でしょうか。食材のイノシシが野生にせよ、飼育にせよ、いやあ〜、いいところですねえ。ちなみに建立は観光ホテルの社長さん。