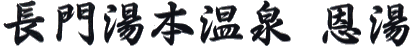
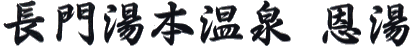
 |
山口県長門市にある湯本温泉市営公衆浴場の恩湯(おんとう)。140円※という破格の入浴料から、それなりの状況を予想して家族同伴を避けていました。数年前にすぐ近くの同じく市営公衆浴場の礼湯(れいとう)が改修されて小奇麗になったので、もっぱらこちらを利用。同じく140円※の入浴料は市営ならでは。しかし、温泉情報誌などを調べるうちに、恩湯に対する認識を改めることになりました。これはタダモノではないぞ。(※2008年4月から200円)

初めての方には場所が分かりにくいかもしれませんね。音信川(おとずれがわ)に沿って並ぶ温泉街のちょうど中央付近に恩湯があります。国道316号線からは、湯本大橋を渡った直後を左折。下関方面からは、大寧寺を通過して温泉街に入ったところで、「←長門湯本駅」の標識の交差点を、駅とは反対方向に右折。画像でワゴン車が右折している路地に入ります。【画像上左】JR美祢線の踏切を渡ると川沿いの温泉街が眼前に現れます。
高層の建物の中で、独特の風貌を備えてこじんまりとした恩湯の建物はすぐ見つかります。赤い「湯本温泉」のネオンが印象的。朱塗りの橋を渡ると左手に駐車場。十分な広さではありません。20台程度かな。【画像上右】土日などの混雑するときは、朱塗りの橋の上まで順番待ちの車が並ぶこともあります。おすすめはやはりウィークデイ。建物前の川岸には、温泉利用の洗濯場の跡が残されています。
券売機でチケットを購入して窓口に差し出し脱衣場へ。広くはありませんし設備もそれなり。豪華風志向の我が家のお嬢さまたちに敬遠されるタイプでしょうね。ま、そんなことはどうでもいいのです。浴場に入ると、正面に2つ並んだ浴槽。それぞれの壁に湯口があって勢いよくお湯が出ています。もちろんかけ流し。浴槽はとても深いので注意が必要。不用意に足を入れるとおぼれるかもしれません……。そんなことはないでしょう。(笑)
湯口のお湯からは、はっきりと硫黄臭を感じ取ることができます。こうでなくっちゃね、温泉は。ただし、温度はそんなに高くありません。むしろかなりヌルめ。こんな温度で風邪を引いたりしないのかな、と思うのは杞憂。長湯をしていると身体の芯から温まってくるので不思議です。深い浴槽で中腰になって心地よい浮遊感に浸っていると、俗世間に疲れた心までが癒されます。
さて、湯上りは例によって源泉の確認と探訪。窓口で源泉について尋ねると意外な反応。至近距離の自家源泉には違いないものの、「どこですか」には「よくわかりません」。はあ。これまでの経験からすると、自家源泉の温泉の方たちは、自慢そうに源泉のことを話してくださっていたのに、恩湯の対応は予想外。挙句の果てに「市役所の温泉係で聞いてください」。そうかあ、市営でしたよね。お役所の窓口なんですよ、ここは。
で、長門市役所に行きました。【画像上】近年の市町村合併で大きくなった長門市では、管内の温泉を管理するために「温泉係」を設置しています。正確には、長門市経済建設部商工観光課温泉係。事前に電話して訪問。名刺を差し上げ、怪しい者ではないこと、調査研究というわけでもないこと、をご説明した上で、部屋の奥の雑然とした机で、温泉係長の福田さんから直接お話を伺いました。いくつかのことが判明。
恩湯の源泉は、湯口付近の地下から湧出。もちろん源泉100%で加温も加水もなし。「浴槽の底からも一部湧出しています」。おっ、そうだったのですか。奇跡と言われる足元湧出にかなり近いのですね。「女湯はどうですか」。同伴した奥さまから、女湯には加温の掲示があると聞いていました。「温泉街のホテルなどに給湯している混合泉を使っています。以前冷たいという苦情があって加温にしました」。
あれれ、男湯と女湯は別のお湯なのですか。温泉係でいただいたチラシにある「源泉かけ流し(加温加水なし)」の記述は男湯だけなのですね。ちょっとマズイのじゃありませんか。チラシでは男湯と女湯の違いは分かりませんよ。「ですから、女湯には加温の掲示を……」。いえ、そういうことではなくて……。一般に女湯の浴場は男湯より狭い、という女性の方の不満を聞いたことがありますが、お湯の質まで違っているとは……。う〜む。
そのほかにもいくつかお話を伺って早々に引き上げました。というのも、足元湧出の情報を得ましたので、一刻も早く現地を再確認したかったからです。長門市役所を出たその足で、再度恩湯に入浴。浴槽をじっくり観察。確かに岩盤の上に直接浴槽があるという感じです。タイル張りの底の一部に岩がのぞいています。右の浴槽の右手前かど。浴槽内にはほかにもそれらしい箇所がありますが、残念ながら気泡の確認などはできませんでした。今後の課題ですかね。

上述のチラシでは、礼湯は「温泉かけ流し(加温加水有)」です。同じかけ流しでも「源泉」と「温泉」を区別しているわけですね。温泉係長さんによれば、礼湯の源泉は礼湯の機械室付近。湯量が十分でないので、混合泉を加えて加温。確かに礼湯の建物を裏の神社から見下ろすと貯湯タンクとボイラーの煙突が見えます。【画像上】
常連のみなさんは気付いていらっしゃるのでしょう、この違い。恩湯に比べて礼湯はいつもお客さんが少ないような気がします。施設や設備の新しさよりもお湯の質。当方、まだまだ修行が足りません。はい。
 |