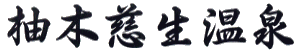
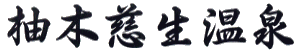
 |
「こんなところはもういやだあ」。ファミリーキャンプで立ち寄った娘たち。たしかにお湯に透明感はなく、湯口でボコボコ不気味な音。しかもそのお湯がかけ流しなので床や壁は清潔感に乏しい。浴槽は狭く十分な洗い場すらない。数少ない蛇口の1つで苦労して髪を洗っていたら隣のおばあさんに睨まれたとか。豪華風好みの娘たちには耐えられなかったらしい。これ以来「温泉」を警戒するようになったのも無理からぬことか。
しかし、そんな温泉も見方が変わると評価は逆転。浴槽は湧出量にふさわしい大きさに制限され、湯口からはガスと共に源泉が湧き出ている。肌にまとわりつく大量の気泡は、このお湯が本物の温泉であることのなによりの証拠。なんといってもかけ流しがすばらしい。ファミリーキャンプの苦い思い出の彼方に忘れ去られていた柚木慈生温泉(ゆのき・じしょう・おんせん)は、新鮮な感動とともにこれまでとはまったく違ったイメージでよみがえってきたのでした。

国道9号線から外れた山間地の道路脇に「柚木慈生温泉」の大きな看板がまず目に入ります。でも、地域の物産を並べた商店があるだけで、温泉らしい施設は見当たりません。しかし、ここが柚木慈生温泉のまさにその場所なのです。商店の前を通り過ぎると、「温泉→」の小さな看板。【画像上左】未舗装の広場が駐車場。奥に進むと、商店の裏手にもう一棟あるのが分かります。これが温泉施設。
「営業時間午前10時〜午後8時」「定休日毎月5日・18日」。この掲示がなければ、誰もここが温泉の入口とは思わないでしょう。民家の玄関そのまんまですから。【画像上右】玄関横へ目をやると、道路向きに「柚木慈生温泉分析」の大きい看板。【画像下左】温泉成分と適応症の記載。普通、分析表はお金を払って中に入らないと目にすることはできませんが、ここは違います。成分に自信がある証拠でしょうかね。

室内にはこんな説明書き。「当温泉は、泉質が高濃度のため源泉100パーセントでは皮膚の弱い人は肌荒れを起こす場合がある。そのために85度の沸かし湯を30パーセントと17.6度の源泉を70パーセントの目安で混ぜ合わせ入浴に適した温度に保ち、常時かけ流しにしている。(温泉専門医のアドバイスによる)平成17年5月 柚木慈生温泉」。【画像上右】温泉法施行規則は、沸かし湯との混合比率の掲示までは求めていませんが、ここまで書かれると、そうですかと納得してしまいます。
さて、肝心の浴槽。自前の写真がどうしても欲しくて事前に計画。平日でも営業開始直後は混み合うので、その一団が去った時間帯。なんとかねばって一人きりになったところで……。のつもりが、最後に二人きりになった相手がつわもの。年輩というほどではありませんが、ひょっとすると温泉通かもしれないという雰囲気。じっくり堪能していらっしゃる感じ。結局、私が根気負けして先にあがることに。こちらが動くと先方も浴槽から出て体を洗い始めました。
ここがチャンスと着衣もままならない姿で引戸を開け、「すみませ〜ん。1枚撮らせてください。そちらは写りませんから大丈夫で〜す」。「ハイ」と、意外にはっきりした同意の意思表示。手早くローアングルからパチリ。立ったままの俯瞰はダメです。湯気でレンズが曇ります。てなわけで貴重な1枚。どなたかは存じませんが、ご協力どうもありがとうございました。右奥が湯口。湯口には時計も。
柚木慈生温泉には湯上りの楽しみがあります。飲泉です。受付で「源泉を飲ませてください」とお願いすると、専用の蛇口から湯飲みに1杯源泉を注いでもらえます。もちろん無料。【画像下左】画像では分かりませんが、湯飲みの内側には気泡がいっぱい。口に運ぶとわずかな硫化水素臭とともにシュワッとした炭酸の味わい。ほお、これが「含二酸化炭素−カルシウム・ナトリウム−炭酸水素塩・塩化物・冷鉱泉」なのですね。

気になるのは源泉地。受付で伺うと、駐車場の敷地内。探すまでもなく、駐車場にゼブラ模様の低い小屋。これです。【画像上右】すぐそばに煙突の出たボイラー室もあります。ここで「加水」「加温」のお湯を沸かしているのでしょう。本物温泉に興味さえあれば、初心者でもそのよさが分かる柚木慈生温泉。「もういやだあ」と言った娘たちにも、早くこのよさが分かるときが来るといいなあ。