 |
 |
駅前でタクシーに乗ればよかったなあ。後悔し始めたのは、加古川駅を歩き出してすぐだった。初めての土地を徒歩で徘徊するのは嫌いではないが、強い夏の日差しで汗だくの上、カメラを入れたバッグが重いのだ。後悔先に立たず。灼熱地獄を歩くこと数十分。やっとの思いで鶴林寺にたどりついた。
写真や図面は、最終的に二次元の限界を超えることができない。是非とも三次元の立体で配管の位置関係を確認したいと思っていた。三段峡駅前のC11189を注意深く観察したこともあるが、朽ち果てて配管の脱落もあり、いまいち自信が持てなかった。忠実に再現された鉄道模型ならどうだ。東京出張の折に、原宿の模型店IMONで、精密仕様のHOゲージC11を、ガラスにくっつきながら観察したが、やはり1/80モデルには限界があった。
壁に突き当たっていたとき、新たな情報をいただいた。加古川市の鶴林寺公園に静態保存されているC11331は、保存状態がよく、補助発電機周辺の配管も正確に分かるとのこと。お送りいただいた画像を見ると、なんと補助発電機の蒸気管は布巻きのまま。その布巻き管をたどれば、配管の位置関係もはっきり分かりそうだ。しかもC11331は、広島機関区のC11330と連番。製造所も製造年もいっしょだ。これは現地を訪問するしかないな。真夏の大阪出張の帰途、加古川駅で途中下車し、鶴林寺を訪問したのでした。

聖徳太子に由来するという鶴林寺には、国宝を初め、数々の由緒ある宝物があるらしい。休息がてら、敬意を表して一応境内に入って散策。お目当てのC11331は、境内を出たところの公園の隅にあった。定期的にメンテナンスがされているのだろうか、三段峡駅のC11189に比べると、保存状態ははるかによい。しかし、フロントの左右に大きな立ち木があり、落ち葉が車体に積もっている。雨滴や樹液はボディによくないだろうなあ。周囲には比較的新しそうな柵があって近づくことはできない。
補助発電機周辺の配管は完璧だ。通風器やコンプレッサの蒸気管だけでなく、水タンクの連通管すら布巻きじゃないのに、どういうわけか補助発電機の蒸気管だけが布巻き。おかげで、運転室の蒸気分配箱まで間違わず追跡できる。なあ〜るほど。これで配管のイメージはバッチリ。配管の取付に着手できるぞ。成果あり。ルンルン。もちろん加古川駅への帰り道はタクシーに乗ったことは言うまでもありません。(古橋さん、どうもありがとう。)

以前取り付けた補助発電機は、塗装に難があったので、塗り直すことに。ブラシでゴシゴシやっている最中、ダミーの六角ボルトの一方が紛失。まあいいか。もう一度作ろう。付属のエルボも利用しよう。ダミーとばかり思っていたら、実は内部が中空で両端がつながっていました。本当の蒸気配管にも利用可能。スバラシイ!

配管の取付にあたって調達した各種パイプ等。左から、3mm×3mm真鍮四角棒、4mm真鍮パイプ、3mm銅パイプ、2mm真鍮丸棒。広島の実家に帰省の折、東急ハンズで購入。

さて、まず最初は、補助発電機のタービンに蒸気を供給する蒸気管の配管から。補助発電機周辺の配管の形状は、機番によって千差万別。C11331の調査を踏まえて、C11328の写真をよく見ると、タービンの下側から横に突き出て、かなり鋭角に曲がっているのが印象的。それにもう1つ。運転室から配管が出てくる位置は、缶被の表面よりかなり上方。そのため、斜めに傾斜した後に缶被の表面に接するようになっている。
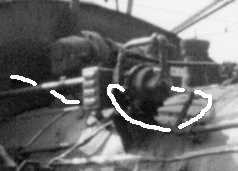
といっても、どこのことだか分かりませんよね。白線の配管が蒸気管と思われます。

2mm銅線を使って試作品作り。C11328の特徴が再現できるように、写真と同じ角度から眺めては、こんな感じかなあ、でも、ちょっとここが……。散々苦労してやっとこんな具合に。もう一度曲げ加工を繰り返す元気がなくなり、試作品がそのまま本採用品に。あはは。

C11328の蒸気管は、写真を見る限り、布巻きではない。しかし、C11331の布巻き管に感動したこともあって、あえて布巻き加工をしました。水タンクの連通管、ドンキーポンプの蒸気管に次いで3箇所目。ただし、管が細いので、バイアステープの幅を半分に。巻き初めと巻き終わりは瞬間接着剤。黒の艶消し塗料をスプレーして出来上がり。

布巻きの蒸気管を取り付けるとこんな感じ。途中1箇所、組立時に余った管押さえ金具で固定。金具は、缶被に2mmのタップを立ててネジ止め。運転室前板には、穴をあけて差し込んでいるだけなので、金具のネジで簡単に脱着。本物に比べるとかなり太い感じですが、そこはイメージ優先の模型なんですから、いいことにしましょうよ。ピッチの細かい布巻きに、我ながら満足。ウフフ。