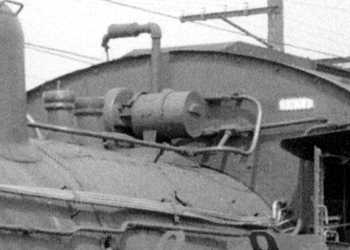 |
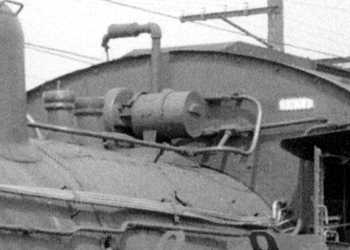 |

発電機ですから電源の出力があるわけです。通気口のある四角い箱の横から出ている配管がどうもそれらしい。C11328では、いきなり垂直に立ち上がって直角に折れ、安全弁と蒸気ドームの間を通って、機関士側から運転室に取り込まれている。

画像の白線の配管がそれ。しかし、補助発電機をやや後方に取り付けたので、同じ配管形状にすることができない。同じようにすると、前側の安全弁に突き当たってしまう。むりやり蒸気ドームとの間を通そうとすると、配管を斜めに取り回すことになる。また、同じように上方に立ち上げると、突起ができるので、引っかけたりして後々面倒なことにもなりそう。困ったなあ。

この箇所だけはC11331をモデルにすることにしました。C11331はサイド水タンクの揺れ止めがあり、補助発電機はやや後方。配管は、まっすぐ前方に延び出てから下方に屈曲。これがちょうど安全弁と蒸気ドームの間の位置関係。ただし、C11331では、蒸気ドームとの間を通らず、主発電機の前を通って機関士側へ。

加工の方針を決め、1mmの針金で具体的に形状を試作。実車では、機関士側の取り込み部分にいくつか分岐があり、やや複雑な形状になっている。しかし、ここは単純化し、突き当たって直角に曲がるだけに。

C11331では、配管が缶被の表面に固定されているが、C11328では、支柱で高い位置に支えられている。2箇所に支柱を設置。【白丸の箇所】砂撒き空気管を取り付けた金具を流用。曲げを伸ばして支柱に。缶被に2mmのタップ。配管の先端は、「架線注意」の下に穴をあけ、差し込むようにした。

どの機番を見ても、配管が直角に曲がるところには四角いボックスがあります。是非これを表現して電源ケーブルの配管らしくしたいと思い、3mm×3mm真鍮四角棒から作成。片側の断面と1つの側面に2mmのドリル穴。断面の穴は、対角線の交点をねらいましたが、微妙に偏心。
正方形の中心に正確に穴をあけるにはどうすればいいのでしょう。4つの辺あるいは角から常に等距離を維持できる工夫ができればなあ。こう回転させて……。ん? そりゃ、旋盤の原理だぜ!!旋盤が欲しくなってきた。

試作品をモデルにしつつ、2mmの真鍮丸棒で配管を作成。キズを付けないように、ペンチは使わず、すべて手曲げ。円弧の箇所はマジックや鉛筆のRを利用。直角部分のボックスは、ロックタイトで圧入。あちこちの方向から眺めながらの曲げ加工は厄介だが、その分達成感もある。この真鍮色は、精密部品の輝きだぜ。

すでに取り付けている支柱に載せ、ハンダで固定。補助発電機側と運転室側の両端は差し込んむだけ。支柱のネジで簡単に脱着できます。

補助発電機周辺はこんな感じ。念のため、汽笛の引き棒を取り付けてみたところ、干渉を避けた絶妙な位置関係にちょっと感動。ほお〜。配管が錯綜した様子もなかなかいい感じ。

こちらは機関士側。直角部分のボックスにご注目。これは電気ケーブルの配管ですよね。他の多くの機番では、室内への取り込み部分にもこのボックスが使用されていますが、C11328にはありません。

艶消しの黒で塗装。いつものことながら、塗装は難しい。表面の一部が荒れてしまった。吹きすぎたのかなあ。

塗装後、再度取付。もちろんピッタリはまる。補助発電機側をローアングルから。

機関士側をローアングルから。缶被から浮いたところはイメージ通り。なめるように眺め回しては、しばし至福の時。ウフフ。