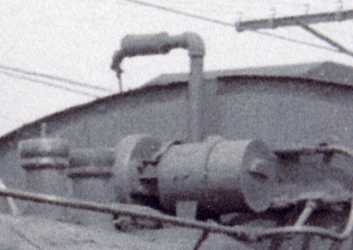 |
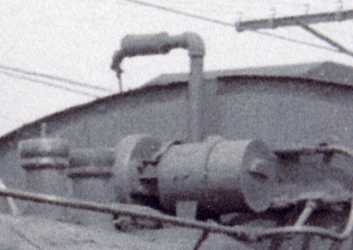 |

作業の手順は慣れたもの。まず、1mmの針金で配管形状のイメージ作り。補助発電機の排気管との違いを際立たせるため、屋根部分のパイプはかなり短い。実車でも、主発電機の排気管の方が短い感じ。

計測したところ、既存の排気管は外径4mm。同様に、延長するパイプは4mmの真鍮パイプ。銅パイプの曲げ加工はすでに経験済みですが、真鍮パイプは未経験。力任せに曲げてみたところ、案の定、うまくいきません。硬い上に、折れて角が付いてしまいます。銅パイプのように焼き鈍したらどうでしょう。割箸の先に取り付けて、キッチンのガスコンロへ。熱のあるうちなら、比較的楽に曲がります。

曲げた部分を中心に、前後を所定の長さにカット。既存の排気管には4mm用のエルボで接続。このエルボもクラウンモデルから入手。排気管の延長に必要なパーツは、基本的にこれだけ。

補助発電機の場合と同様に、屋根に2mmのタップを立てて支柱を取り付け、パイプをハンダ付け。支柱は補助発電機の支柱より高くしました。真鍮パイプとエルボはロックタイトで固定。既存の排気管には差し込むだけ。脱着可能。そのために、エルボの内径を4.1mmに拡大。4.0mmで密着していたものが、4.1mmだとガポガポ。0.1mmの差は歴然。0.1mmは決して小さな数値ではないと実感。

取り外して塗装。塗料がムダになるようで気が引けますが、やはり遠くに離してスプレーするのがコツなんでしょうね。まあ合格点の仕上がり。でも65点くらいかな。塗装が課題だなあ。

再び取り付けて出来上がり。エルボ部分は、屋根の取付ネジから離れていますが、差し込むだけでしっかり固定されています。

どうですか、このアングル。ウフフですよね。主発電機の4mmの排気管と補助発電機の3mmの排気管が、高さの違う支柱に支えられて立体的。視点を変えながら、時間を忘れて、なめるように見回してしまいます。ウフフッ。(笑)

C11330ではこんな感じ。我ながら排気管フェチの心境で〜す。(笑)

|