JR線路のレールの一例【画像下左】。JR可部線大町駅。白枠箇所を拡大すると……【画像下右】。レール上面の内側半分が輝いている。もう一方のレールは輝きの幅が広い。私のイメージもこんな感じだったので、当初レールの塗装はこんな感じにしようかなと思っていた。しかし、庭園鉄道の車輪の接触具合がJRと同じとは限らない。レールを踏みつけてしまうこともある。レール上面の塗装は剥がれるリスクが大きい。

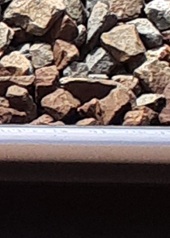
JR線路の別の一例【画像下左】。大町駅の隣りの緑井駅。上面全体が輝いている。車輪が幅広くレールに接しているのだろう。島式ホームの周辺レールを見回してみると、どこもこんな感じだ。必ずしも大町駅のような感じではない。そして、もう1つ別の例【画像下右】。これは広島電鉄の路面電車の線路。こちらもレール全体が輝いている。狭軌のJRに比べて標準軌の幅広感がわかる。


これら以外の場所を見ても、レールの輝き幅はさまざま。気にしなくていいのではないか。むしろマスキングテープを貼る手間と塗装後のことを考えると、上面全体にテープを貼っていいだろう。ただし、フランジと接する内側に気持ち寄せることにしよう。庭園鉄道のレール塗装は、こんな観察に基づいている。


ところで、緑井駅で木製枕木を発見!レール継目の下に1本【画像上左】あるいは2本【画像上右】。理由はいくつかあるようだが、それより、現役枕木の色調が気になった。目下使用中のアサヒペンツヤ消しこげ茶よりやや濃く暗い感じ。つまり、当鉄道の枕木は経年によって色あせてサビ色になったという感じかな。さて、側線の塗装。直線線路はこれまで通りだが、新たに曲線線路が1本ある。

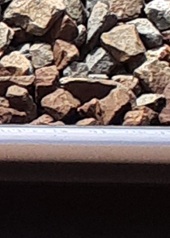
JR線路の別の一例【画像下左】。大町駅の隣りの緑井駅。上面全体が輝いている。車輪が幅広くレールに接しているのだろう。島式ホームの周辺レールを見回してみると、どこもこんな感じだ。必ずしも大町駅のような感じではない。そして、もう1つ別の例【画像下右】。これは広島電鉄の路面電車の線路。こちらもレール全体が輝いている。狭軌のJRに比べて標準軌の幅広感がわかる。


これら以外の場所を見ても、レールの輝き幅はさまざま。気にしなくていいのではないか。むしろマスキングテープを貼る手間と塗装後のことを考えると、上面全体にテープを貼っていいだろう。ただし、フランジと接する内側に気持ち寄せることにしよう。庭園鉄道のレール塗装は、こんな観察に基づいている。


ところで、緑井駅で木製枕木を発見!レール継目の下に1本【画像上左】あるいは2本【画像上右】。理由はいくつかあるようだが、それより、現役枕木の色調が気になった。目下使用中のアサヒペンツヤ消しこげ茶よりやや濃く暗い感じ。つまり、当鉄道の枕木は経年によって色あせてサビ色になったという感じかな。さて、側線の塗装。直線線路はこれまで通りだが、新たに曲線線路が1本ある。
 曲線線路は新品なので水洗いはせず、青ニス除去スプレーとペイントうすめ液で脱脂洗浄してレール上面をマスキング。曲線なので位置決めしながら少しずつ貼っていく。
曲線線路は新品なので水洗いはせず、青ニス除去スプレーとペイントうすめ液で脱脂洗浄してレール上面をマスキング。曲線なので位置決めしながら少しずつ貼っていく。
|
 3本目は線路の向きを換えて作業。慣れると要領がわかる。
3本目は線路の向きを換えて作業。慣れると要領がわかる。
|
 マスキング完了。
マスキング完了。
|
 曲線線路のスプレーも直線線路と変わらない。レールと枕木の隙間に吹き残しができやすい。
曲線線路のスプレーも直線線路と変わらない。レールと枕木の隙間に吹き残しができやすい。
|
 マスキングを剥がして塗装完了。
マスキングを剥がして塗装完了。
|
側線の末端に車止を設置したい【画像下左】。レールを丸く山型にしたものや直線レールを組み合わせたものが思い浮かぶが、庭園鉄道では避けた方がいい。線路面から突出した構造物には接触のリスクがあるからだ。
暴走した車両を止めるわけではない。線路の末端に不用意に接近したときに、それとわかるものをを設置したい。そもそも機関車や乗用台車が暴走するようなことはしないし、線路の末端まで進むこともない。これまでの運転会でもそうだった。レールの上面に突起物を設置する程度で十分だろう。


レール上面に角棒を取り付けるのはどうか。小川精機のレール断面はこんな形状【画像上右】。明治の鉄道開通を思わせる双頭レールだ!なぜこの形状なのか、小川精機に確認してみたい気もする。それはさておき、この上面に角棒を載せるとすればその大きさは?
上面の左右にアールが付いている。平らな部分に載せたい。最大幅は6.0mm、アール部分を除いた平らな上面は5.0mm。手元にある4.0mm×4.0mm角棒でいいかな。ちなみにレールの全高は15.0mm、頭の縦幅は4.0mm、首の横幅は2.8mm。ネジ止めするならこれらの数値も気になるところ。取付ネジはM1.7mm、L=8.0mmかな。
転轍装置の作成で使った角棒を利用する。30mm程度に糸ノコでカットしてボール盤で端面仕上げ。3本作るならできるだけ長さを揃えたい。誤差を攻める。
29.95mmから30.05mmの間に収めた。誤差0.1mm以内だ。デジタルノギスの数値だけでなく、切粉(きりこ)の量で削った長さを推測する。久々にウフフ!。
長さが揃うと、いっしょにまとめてバイスに固定できる。ネジ穴の位置のケガキ。所定の幅のアルミアングルを置いてスジを引く。
横スジを入れて穴位置を決める。これにはディバイダー。両側から引いて中心を確認する。
最初にネジの下穴と同じ1.4mm。これも3つまとめてボール盤で。
角棒のそれぞれに刻印。ネジ穴を写し開けるので、区別できるようにしておく。角棒完成。
次にレール側のネジ位置を決める。左右の車輪が同時に角棒に当たるためには、角棒がレールと直角に横一直線に並ばなくてはいけない。ここの線路は切り詰めているので、レールの端が不揃い。どうすればいいのか。スコヤを使用してガイドのアルミバーを固定した。
ガイドバーに当てて角棒を置き、片方のネジ穴位置をレールに写す【画像白丸】。一度に2つ写すとズレるので、まず1つだけ。
レールのネジ位置にボール盤でドリルを立てるのだが、長いレールの固定に一苦労。段ボール箱を重ね合わせ、水準器でレベルを確認する。
レールのネジ切りに先立って、タップガイドを作成。以前作ったM6.0用のタップガイドにM1.7mm用の穴を開ける。トースカンで角パイプの上下2面に穴位置のスジを入れる。
鉛直線上に上下2つの穴があるだけだが、タップガイドの効果は絶大。フリーハンドで鉛直にタップを立てるのはとても難しい。素人には無理だ。
タップガイドを利用してレールにM1.7mmのネジを切る。
角棒の穴を1.7mmに拡幅し、レールにネジ止め。
ボール盤でもう一方のネジ穴を写し開ける。ネジ止めしているので穴位置がズレることはない。
L=8.0mmのM1.7mmネジが足りなくなった。長いものを削って短くすることにした。4.0mm角棒を2つ重ねて8.0mm。ネジ切りして固定し、飛び出たところを削り取る。褶曲した角棒は、転轍装置のトングレールロッドの試作品の一部。
下がL=8.0mmに削ったM1.7mmネジ。上は元のL=10.0mm。
写し開けた下穴にタップを立てて組み立てれば作業は完了……。ヒィ〜ッ!!なんてこったあ、タップが折れた(涙)。タップガイドを使用して慎重にネジ切りしていたのに……。しばし呆然。仕方がない。なんとかしましょう。

車止のテスト
車止の効果を検証するために、塗装前にテストを実施。すでに塗装済みの線路を敷設して乗用台車を乗り入れた。車止は乗用台車を止められるのか。止まらない場合どんな事態になるのか。興味津々。
側線の末端に角棒の車止を設置。高さ4.0mmなので、ほとんど目立たない。
タップが折れた箇所はどうなったのでしょう。一方のネジ位置が変わっていますね。タップの先端が折れ込んでいるので、同じ位置にネジ切りはできません。問題のネジ穴は、真鍮線を入れてハンダで埋めました。ヤスリで仕上げれば跡形もありません。おそらくこのホームページを見た人以外は気付かないでしょう。(笑)
さて、車止の効果の検証です。乗用台車は止まります。ただし、極低速の場合です。
拡大すると、車輪が左右同時に角棒に当たっているのがわかります。ヨシ!
しかし、ある程度の速度があると簡単に乗り上げてしまいます。乗り上げた後どうなるかは、もういいでしょう。これは空車の場合。人が乗っていると、ある程度の速度があっても乗り上げません。ゴツンと止まります。上向きのベクトルが押さえられるからでしょう。そうなると横向きの力が気になりますね。取付ネジの強度が心配。
車両を車止に当てて止めることはありません。手前で停車します。実物の車止もそうですよね。万一勝手に転がっていっても脱線しないで済む、そんな程度で十分です。検証の結果、車止は一定の効果アリです。
最後に線路の塗装。枕木にサビが出ているので、一応サビ落とし。「サビ落とし不要」の塗料とはいえ、表面をできるだけフラットに。
ペイントうすめ液で洗浄。
車止部分の塗装をどうするか。車両が来ないのが前提ですからレール上面はサビ色。どこまで?考えても決まらないので、えいやーとスケールの幅に。
レール上面のマスキングテープを取り除く。

車止

側線の塗装完了

側線ポイントヨシ!
