すでに
橋桁の塗装を施工しているが、全線にわたる大規模な塗装工事は庭園鉄道始まって以来。ワフやホキの塗装からもう20年あまり。塗装の基本を確認しつつ作業を進めたい。手掛かりは上掲『技術シリーズ 塗装(普及版)』2005年。ワフ塗装の際に入手して勉強した(ちょっとだけ)。塗装は難しい。塗料の分類・区分も厄介だ。用語がたくさんあって使い方が錯綜している。自分なりに整理して理解しようとしたが、我が身の至らなさを痛感する。
塗料の主成分は次の3つ。
①塗膜成分(油脂、セルロース、合成樹脂など)、
②蒸発成分(溶剤)、
③発色成分(顔料)。とりわけ塗膜成分を流動化する溶剤は、強烈な臭いや毒性があって注意が必要。単発の小パーツの場合はさほどでもないが、継続的な塗装作業では本格的な対策をした方がいいだろう。また、塗膜成分によって溶剤の種類が異なる点も要注意。油性塗料には
ペイントうすめ液(石油系シンナー)、ラッカー塗料には
ラッカーうすめ液(ラッカーシンナー)。
一番の問題は色。何色を選択すればいいのか悩ましい。枕木とレールを塗り分けるつもりはない。かつて年期の入った枕木がサビ色になっているのを見かけたものだ。枕木とレールを兼用できるのは何色なのか。ホームセンターで物色したものの、最適解は得られなかった。えいやーで決めたのがこちら。
アサヒペン油性高耐久鉄部用スプレー(300ml)ツヤ消しこげ茶【画像左】。ツヤ消し黒【画像右】。

コンプレッサーを使用したスプレーガンも考えたが、
粘度の調整に腰が引けて、安直なスプレー缶にした。決め手は「高耐久」と「サビの上からそのまま塗れる」「サビ落とし不要」のうたい文句。塗膜成分は合成樹脂(シリコンアクリル樹脂)。顔料に加えて
サビドメ剤。溶剤はペイントうすめ液。しかし、発色は実際に塗ってみないとわからない。とりあえず1缶だけ入手して使ってみることにした。
いきなり線路というわけにもいかないので、転轍装置のパーツから。小さいものは割り箸の先に取り付けた【画像左】。比較的大きいものはネジ穴に針金を通して吊るした【画像右】。これで塗装の準備完了。もちろん事前に
脱脂しておく。


転轍装置のパーツは、スライドバーの床板も含めてツヤ消し黒【画像左】。同様にLリンク、トングレールレバーのロッドもツヤ消し黒。Lリンクの床板だけツヤ消しこげ茶【画像右】。床板は枕木の延長のイメージ。ツヤ消しこげ茶はこんな感じなんだ。
クレオソートがたっぷり染み込んだ真新しい枕木かな。


さあ、本番の線路の塗装……、というわけにはいかない。線路は橋桁よりも長くて重い。塗装スペースがそのままでは使えない。線路用に拡充する必要がある。
 線路(L=1500mm)を塗装するためには、フックを取り付けたアングルをさらに上方に上げる必要がある。それに合わせて飛沫防止のコンパネをもう1枚追加。実際に線路を吊るして様子を見る。
線路(L=1500mm)を塗装するためには、フックを取り付けたアングルをさらに上方に上げる必要がある。それに合わせて飛沫防止のコンパネをもう1枚追加。実際に線路を吊るして様子を見る。
|
| |
 フックは最短位置に変更。Sカンも短いものに。
フックは最短位置に変更。Sカンも短いものに。
|
| |
 問題は線路の重量。直線線路は重さ10キロ。ポイントは重さ20キロもある。これに耐えられるように重しのブロックを追加した。これまではアングルの自重だけだった。アングルの支点もブロックで嵩上げ。
問題は線路の重量。直線線路は重さ10キロ。ポイントは重さ20キロもある。これに耐えられるように重しのブロックを追加した。これまではアングルの自重だけだった。アングルの支点もブロックで嵩上げ。
|
| |
 塗装に先立つ下準備のための作業台を新設。長椅子の上にアルミ棚板(L=1500mm)を載せた。いずれも家にありました!
塗装に先立つ下準備のための作業台を新設。長椅子の上にアルミ棚板(L=1500mm)を載せた。いずれも家にありました!
|
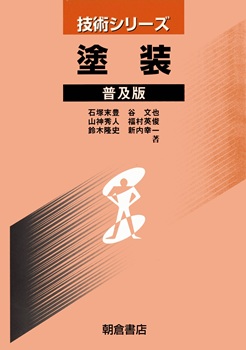
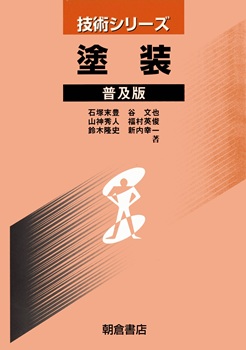


線路(L=1500mm)を塗装するためには、フックを取り付けたアングルをさらに上方に上げる必要がある。それに合わせて飛沫防止のコンパネをもう1枚追加。実際に線路を吊るして様子を見る。
フックは最短位置に変更。Sカンも短いものに。
問題は線路の重量。直線線路は重さ10キロ。ポイントは重さ20キロもある。これに耐えられるように重しのブロックを追加した。これまではアングルの自重だけだった。アングルの支点もブロックで嵩上げ。
塗装に先立つ下準備のための作業台を新設。長椅子の上にアルミ棚板(L=1500mm)を載せた。いずれも家にありました!
古い線路はサビだけでなく、土や砂なども付着している。作業前に水洗い。
塗装は下地、下準備で決まる。まず、レール上面の脱脂から。車両が走行するとゴミや油分が付着する。頑固な油分には青ニス除去スプレー。金属の脱脂洗浄にも使えます。
次に、枕木とレール側面をペイント薄め液で脱脂洗浄。青ニス除去スプレーでもいいが、大量の使用は有害性とコストが気になる。
そして、レールのマスキング。レール上面は金属光沢ですよね。6.0mmのマスキングテープを使用。テープの位置は車輪フランジの内側寄りをイメージしましたが、あまり気にしないことに。走行するとまたゴミと油にまみれる。
フックに吊るす。フックの位置が高くて、しかも線路が重いので苦労する。Sカンがうまく入らない、うぐぐっ……
ツヤ消し焦げ茶で、枕木の上面、レールの側面を吹く。クルッと回転させて裏から枕木の側面。上下を吊り直してもう一度同様に。吹き残しがないかよく確認。レールが突出しているので、陰ができやすい。
一晩おいて作業台に戻し、転轍装置の引棒支えを塗装。ツヤ消し黒を刷毛で重ね塗り。スプレー缶の吹口に刷毛を当てて塗料を移す。小さいパーツなので少量でOK。線路の塗装はこれで完了。
線路を取外したついでに、橋桁を再塗装。砂の堆積と汚れが目立ち、いつの間にか塗装にキズもある。
橋桁に線路敷設。まだらだったサビが跡形もなく消えて、まあいい感じかな。
線路継目のボルト、橋桁への取付ネジの頭も同色に。これもスプレー缶の吹口から塗料を移して刷毛塗り。新品ではないので、レール上面の光沢はイマイチですね。
整備場の線路は半分だけ塗装。左半分が塗装済み、右半分はサビのまま。若干色調と質感に差がありますが、まあこれでいいことにしましょう。試行塗装終了。次回から本施工だ。
