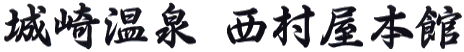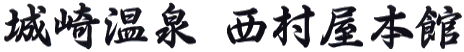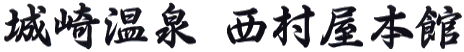
京都の大学に進学した娘の入学式に出席した帰り、奥さまと二人で城崎温泉に寄り道することにしました。なんでも奥さまのお気に入りの定宿があるのだそうで、今回で3回目とか。チケットの手配など、すべてお任せで同行させていただきました。温泉求道者の私としては、歴史と由緒のある著名な温泉地を探訪する絶好の機会。


行きの列車は京都駅始発、山陰本線経由の「きのさき1号」。車両は旧国鉄色の183系。【画像上左】温泉とはまた別に、これはこれで楽しめますね。ちなみに乗車したのはクロハ183-803。もちろんグリーン席ではなくて普通席。(笑)上機嫌の私とは逆に、「シートが狭くてガタガタするね」と奥さまはやや不満げ。そりゃそうですよ、年代モノの車両ですからね。2時間半足らずで城崎温泉駅に到着。【画像上右】あいにくの小雨模様。
平安時代以来の歴史をもつ城崎温泉は、静かな流れの大谿川(おおたにがわ)に沿って温泉街が続いています。7つの外湯があることでも有名。通常は入湯料を払って入りますが、宿泊者は宿でタダ券がもらえます。駅のすぐ隣りのさとの湯。以下、川に沿って上流へ、地獄湯、柳湯、一の湯、御所の湯、まんだら湯、鴻の湯。いずれも建物は新しいですが、それぞれ由緒のあるもののようです。
 さとの湯
さとの湯
|
|
 大谿川(おおたにがわ)
大谿川(おおたにがわ)
|
| |
|
|
 地獄湯
地獄湯
|
|
 柳湯
柳湯
|
| |
|
|
 一の湯
一の湯
|
|
 御所の湯
御所の湯
|
| |
|
|
 まんだら湯
まんだら湯
|
|
 鴻の湯
鴻の湯
|
今回のお宿は西村屋本館。まんだら湯の近くで、これもまた由緒のありそうな日本建築の旅館。【下画像玄関】ふう〜ん、奥さまはこういうのがお気に入りなんですね。すべてお任せなので、料金は分かりません。江戸時代後期の創業、中庭に面した客室の配置など、山口湯田温泉の松田屋とよく似ています。奥さまのお話によると、とりわけ下足番のおじいさんがお気に入りとか。しかし、今回はお会いできませんでした。すでに引退されたとのこと。残念。

チェックインして部屋に案内された後、早速浴室チェック。玄関横に比較的大きめの浴室が2つ。【下左右画像】これは、毎日男女入替。そして、迷路のように続く廊下の一番奥の建物にも、比較的小さめの浴室。いずれの浴槽もそんなに大きくはありません。浴槽は小さい方がいい。宿の入湯は後回しにして、外湯に出かけました。もちろん7つ全部なんて無理。ま、1つだけでいいでしょう。最寄りの鴻の湯へ。効能に夫婦円満とありましたので。(笑)


さて、温泉求道者としての泉質チェック。鴻の湯の近くに「城崎温泉薬師源泉」があります。「城崎温泉元湯」とやぐらのような建物。【下画像】しかし、「元湯」と言っても、こんな風に岩の先端の丸穴から源泉が湧出するはずはないので、これはあきらかに人工のモニュメント。隣りのやぐらの中で揚湯ポンプが稼動しているのをガラス窓越しに確認できます。

自然湧出量150リットル/毎分、揚湯量400リットル/毎分、湧出温度81.0℃、掘削深度500メートル、という表示。お湯は鴻の湯の裏の貯湯タンクに送られていることも明記されています。なるほど。確かに鴻の湯の温泉分析表によれば、お湯は複数の源泉の混合泉。実はその後の調べで、城崎温泉全体が集中配湯管理であることが判明。宿や外湯のお湯も元は同じ混合泉というわけです。
鴻の湯だけでなく、宿泊した西村屋本館のお風呂も、いずれも加水、循環、塩素。限られた湧出量を多くの施設で利用すれば必然的にこうなるのでしょうね。志賀直哉の小説など、温泉地としてのネームバリューはともかく、泉質マニア的には……。ただ1点、救われたのが薬師源泉のそば、温泉寺境内の飲泉場。おそらくこの飲泉のお湯は源泉そのものなのでしょう。まったりした感じの食塩泉であることが確認できました。この源泉だけを使った小さい浴槽が1つだけでもあればなあ……。
残念ながら、当方の「本物の温泉」には登録できませんね。西村屋本館にしても、料理、接客、建物の風情など、温泉地の宿として申し分ありません。でも、温泉地の本質は温泉、それも温泉の泉質にあるはずですよね。多くの訪問客が求めているのはそうではないということでしょうか。建物や設備は不十分でも、別府の泉質のすばらしさを改めて思い起こしました。あ、でも、大谿川沿いの満開の桜はすばらしかったです。
〔おまけ〕 帰りの列車は「北近畿12号」。福知山線経由の新大阪行きです。行きと同じ旧国鉄色の183系。【下左画像】乗車した車両をよく見ると、行きと同じクロハ183-803。もちろん帰りもグリーン席ではなくて普通席。(笑) 山陰本線(京都−福知山−城崎)、福知山線(大阪−福知山)、舞鶴線(綾部−東舞鶴)、宮福線(福知山−宮津)が、福知山で交差、結節する北近畿の鉄道網は、「ビック・エックス」と呼ばれているのだそうです。


新大阪の新幹線乗換に余裕があったので、大阪で途中下車してなんばに立ち寄りました。お目当ては、法善寺横丁の夫婦善哉。同僚の先生にすすめられて織田作之助の小説を読む機会があったので、その現地調査。(笑)一人前の善哉を2つの椀に分けて出すところから夫婦善哉。【上右画像】2つに分けるとたくさん入っているように見える、と考えたのだそうです。一人前を2人で食べるわけではありません。小豆がしっかりしていて甘すぎず好印象。メニューはこれだけ。
夫婦善哉をカップルで食べると円満になれるのだそうです。城崎温泉の鴻の湯の夫婦円満との相乗効果で、我が家もしばらくは大丈夫かな。(笑)