





キャップを拡大するとこんな感じ。デジタルノギスで計測すると、厳密にはやや気持ち先細りです。

ボールペンを2本購入。U字型にこそなりませんが、縦方向は中心を外して大きめにカット。
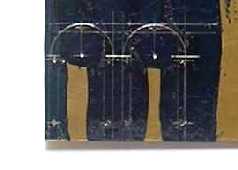
側板に取り付ける基盤は、0.5mmの真鍮板から作成。切り出す前に取付用の下穴も。

薄板のヤスリがけには気を使います。直角方向に安易に削ると変形します。LとRの刻印も優しく慎重に。

後付の安全装置だからでしょうか。調べた限り、取付位置は車両ごとにまちまちです。車掌室の中央部分に付いている車両もあります。ここでは、一応あんみつ坊主さんご提供のワフ29513を念頭に位置決めをしました。いつもの通り、青ニスとバスコークで所定の位置に接着。

取付穴を側板に写し開けて、M1.2mmタップ。この5箇所のネジ頭の突起も、信号炎管被をそれらしく見せる特徴です。

ボールペンのキャップから切り出した被の部分をバスコークで基盤に接着。これで信号炎管被の出来上がり。色は別として、それらしく見えませんか。

右側の信号炎管被のアップ。

これは左側。先端の丸みと5つの取付具の突起がポイントです。

|